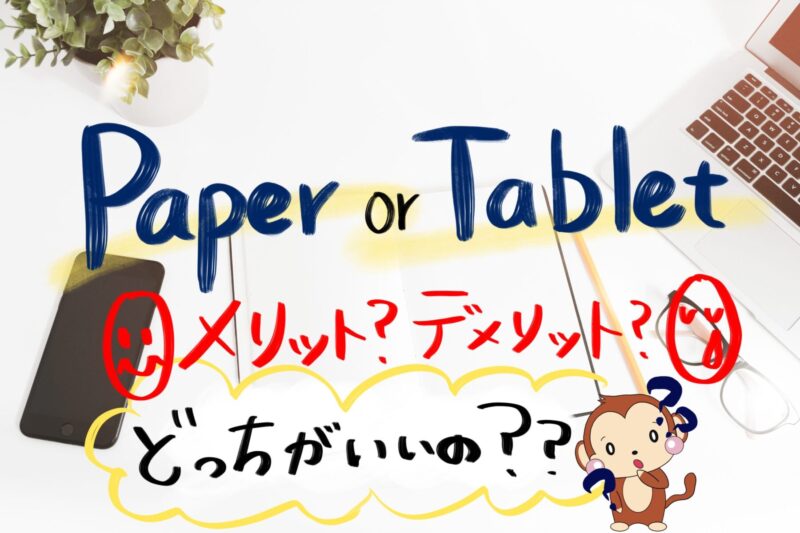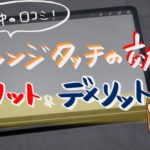最近の勉強法というのは実に近代的になってきていますよね。
学校でもタブレット導入が始まっているところもあるようで、政府もタブレットで授業を受けることを推奨しており
いよいよ本格的に学習の仕方というものが変わってくるなと感じます。
- 昔ながらの紙やノートを使う紙学習
- 新しく導入されるタブレット学習
この2つについてみなさん考えたことはありますか?
親としては楽に感じるのはタブレット学習ですよね!
子供の興味を引いてくれて学習の説明も丁寧、そして自動丸付け機能と大人も子供も魅力が詰まってる!
でも紙やペンに慣れ親しんできている事やタブレットの購入や故障した場合を考えるとなかなか導入に悩んでしまいますよね。
ポイントを簡単にお話しすると勉強に慣れていて、長く記憶に残し定着させたいなら紙学習の方が、
勉強すること自体が苦手で、飽き性なタイプの子にはタブレット学習の方が優れています。
しかし私は紙とタブレットのいいところ取りをする方が親子ともども負担も少なく楽しみながら続けやすいのではないかと思います。
理由は紙、タブレットどちらのメリットも取り入れることで理解力が深まり記憶に残るよう働きかけも可能だから!!



どちらかを選ぶにしてもメリットやデメリットを通して上手く選択していくことが必要だなと感じたので是非本文をご覧ください。
タブレット学習




タブレット学習のメリット
タブレット学習のメリットは私が考えるに以下の5点にまとめられると思います。
ココがおすすめ
- 子供の興味を引き自主的に勉強を始める
- アニメーションなどのわかりやすい解説がある
- 採点が早いので正しい書き順や解説をすぐ確認できる
- 端末さえあれば学習できる
- 子供の苦手傾向や学習進歩が確認できるサービス
子供の興味を引き自主的に勉強を始める
これは我が家がタブレット学習を始めてすぐに効果を感じたところでした。
我が家ではiPadなどを使いYouTubeを見たり、知育系アプリを使わせたりしていたのでタブレットの操作も問題ありませんでした。
むしろ自分専用タブレットを持てたことに大喜び!!
毎日暇さえあればタブレットを開き何かしらの勉強をしていました。

アニメーションなどの分かりやすい解説がある
これはタブレットならではの利点だと思います。
間違えた問題について「なぜ」「どうして」を子供がわかりやすいように説明するのって難しいんですよね。
精一杯教えても「どうしてそうなるの?わかんない(;_;)」と泣かれ、親もストレスになり悪循環。
これでは楽しく学ぶことはできませんよね。
タブレットの場合はきちんと専門家が子供のわかりやすい言葉を使い、アニメーションや図を使って目でも理解することができます。

採点が早いので正しい書き順や解説をすぐ確認できる
親が丸つけ作業をする場合どうしても常にスタンバイしておくことが難しく、問題を解いてから間違えている事に気付くまでのタイムラグが起きてしまいます。

そうなると例えば漢字学習をしている場合書き順まではどうしても確認できません。
その点タブレット学習だと書き順が正しいかどうかも判断して教えてくれますし、
答えがあっているかどうか間違えたら解説や解き方のポイントなどをすぐに教えてくれます。
間違えた問題の復習を自動ピックアップ出来たりするものも!!
間違いは早いうちに正しい情報に置き換えられれば、つい間違えることやどっちだっけ…などの混乱も避けられます。
端末さえあれば学習できる
例えばドリルやプリントを教科ごとに準備するとなるとかなりの量になります。
タブレット学習なら必要なのはタブレットだけ!
何教科でもタブレットの中で保管する事ができるので、兄弟が多い家族でもそれぞれの子の教材の管理する手間もなくなります。
また、タブレットさえあれば勉強する事が可能なので場所を選ばずに学習に取り組むことができます。

子供の苦手傾向や学習進歩が把握できるサービス
「タブレットだと1人で黙々と取り組めそうなのは分かった。
でも本当にちゃんと勉強してるの?どんなところが苦手なの?」などが気になってきますよね。
導入する教材によって保護者向けに学習進歩や、苦手分野の確認ができるサービスがあります
現在の状況がデータでまとめられているので声かけや、間違いの多い問題をやらせてみたりと様々なアクションを起こすことができます。

タブレット学習のデメリット

一覧にするとこんなデメリットを感じたよ!

ココに注意
- 本体購入やレンタルする必要、また故障などのトラブル
- ゲーム感覚になって身につきづらい
- 選択問題での回答が多い
- サービス終了の可能性も0ではない
本体購入やレンタルする必要、また故障などのトラブル
まず本体購入やレンタルについて。
これは言わずもがなタブレット学習を始めるに当たってぶち当たる最初の壁です。
手持ちのタブレットやパソコンで受講可能な所もありますが、子供専用を用意している家庭はなかなか少ないのではないでしょうか?
兄弟で取り合いになったり、保護者の方が必要になったりなかなか共用するのは難しい印象です。
でもタブレット高いですよね…この初期費用が最初のネックかなと思います。
タブレット導入を考えていて悩んでいる方におススメなのは進研ゼミのチャレンジタッチ!
\専用タブレットが0円で借りられるのは進研ゼミだけ!本体保証も安い!/
進研ゼミを実際に利用してみて感じたメリットなどをまとめている記事はこちら♬
-

【受講なうの口コミ】チャレンジタッチの効果は?メリットとデメリット、感想をぶっちゃけレビュー
チャレンジタッチを受講した効果 我が家ではチャレンジタッチを年長の時に受講開始しました。 気付いたら勉強してる 迷うほどのコンテンツ量! 「できない」が「できる」に! 自分で考えて理解するように! も ...
続きを見る
そして子供の使うものですから故障も頭に入れておかないといけません。
落として画面が割れた、ディスプレイが反応しなくなったなどなど。

ゲーム感覚になって身につきづらい
たくさんのアニメーションやキャラクターの説明のおかげで分かりやすい解説になっているのですが、
その代わり本当にアニメを見ているだけの感覚、問題を解く時はゲームで答え探しをしている感覚に。
これは勉強だ!と意識すると楽しくなくなってしまいそうですが、遊びの感覚が強いと頭に入らずその場のみになってしまう懸念があります。

選択問題での回答が多い
タブレット学習の場合、問題の解答方法が選択問題になっていることが多い印象です。
これが先ほど言ったようにゲームやクイズ感覚に陥る原因だとも思います。
算数の場合は式を書いてから問題を解き答えを出す、が一連の流れですがタブレット学習の場合1〜4の中から答えを選ぶだけ。
適当に選んでも4分の1の確率で正解になってしまいます。
これでは理解していることにはなりませんね。
サービス終了の可能性も0ではない
過去受講期間中の復習は○年まで振り返って学習可能というところが多いですが、
その◯年先までその会社のタブレット学習サービスが続いてるかは誰にも分かりません。
突然のお知らせでサービス終了のお知らせが来ることも0ではないことを頭の片隅にでも入れておく必要はあります。
※なくなる事を示唆している訳ではありません。


これまでのメリット、デメリットを参考にすると
タブレット学習に向いているタイプ
- 物を大事に扱い、終わったらきちんとしまえる子
- 勉強することに苦手意識が強い子
- 飽きやすい子
- これ以上家に物を増やしたくない
- 保護者に忙しく勉強に寄り添う時間がない
以上のような家庭が向いているなと感じました。
タブレット学習専門でオススメの教材は進研ゼミのチャレンジタッチ、スマイルゼミ!
値段で選ぶなら最安値はスタディサプリ!
でもこちらは小学4年生~となっていますので低学年のうちは使えません。
続いて紙学習についてもまとめてありますのでどちらがより合いそうか比較してみてくださいね♬
紙学習


紙学習のメリット
ココがポイント
- 電波状況や充電などの心配がない
- ドリルやプリントを始め種類が豊富
- 書く作業をすることで記憶へ残りやすい
- 理解しようとする力、集中力が高まる
- 紙が主流のテストに備えられる
電波状況や充電などの心配がない
これがタブレットと比較し1番に大切なポイントかなと思い最初に持ってきました。
電波状況については使う教材によりダウンロードしてできる(できる範囲は狭まる)物もありますが、
電池に関しては切れてしまえば使えません。
一方紙学習であればそのような心配なく鉛筆と紙(ドリルやプリント)さえあればいつでも学習が可能です。

ドリルやプリントを始め種類が豊富
昔から使われてきている紙学習なのでたくさんの会社から選びきれないほどの教材が書店を始め身近に売られています。

今ある教材から選ぶ必要があるよ。
その点紙学習ならその時子供が必要な教科だったり範囲(漢字、解読力、暗記系など)を個々にチョイスして安価で手に入れることができます。

書く作業をすることで記憶に残りやすい
紙学習の場合文字を書き図を書き、自分で手を動かしながら学習していくので脳に学習の記憶が残りやすいと言われています。
実際暗記したいと思った時に声に出して何度も読んだり、何度も繰り返し紙に書いたりなど物理的な動きをすると思います。
アメリカのある大学の研究者の結果では紙に手でノートをとる学生の方が成績が良かった、と発表があったようです。

タブレットのようにタップ、スワイプ作業だけではなかなか記憶の定着までは結びつきにくなるのはなんとなく理解できますね。
理解しようとする力、集中力が高まる
タブレットの場合解説に音声や動く図、アニメーションを含むために動画視聴をしている感覚に陥ることがあります。
一方紙学習の場合自身で文章を読みかかれていることを理解して解いていく必要があります。
読み上げ機能が付いているタブレット学習とは違い、紙学習の方が理解する為に集中する必要がありそのおかげで理解力が伸びていくというわけです。
集中力については子供の場合十数分程度、その後はその子次第といわれています。
でもゲームをやらせると長いこと熱中してやっている子供も少なくないですよね?
それと同じで子供もやり方次第でもう少し長い時間集中させることが可能では?と感じています。

紙が主流のテストに備えられる
タブレットが導入されてきていると言ってもテストの主流はやはり紙ばかりが目立ちます。
字を書く事に慣れていないと書き方やバランスが取れないために枠内で収まらず書き直しが必要になる手間が起きることも。
選択問題になれているタブレット学習の子供と、字を書くことになれている紙学習の子供を比較すれば自ずと紙に慣れている子供の方が優勢なのは理解できると思います。
書く力というものは紙に字を書いていくことで伸びると言われており、国語のような文章を必要とする問題にはやはり地震で読む力、書く力が必要になります。




紙学習のデメリット
良いところが多かったように感じる紙学習ですが、デメリットもやはりありますので報告させてください!
ココがダメ
- 物理的にかさばる
- 書き込むと見にくくなる
- 書く事が面倒になる、飽きる
- 復習のムラ
- バックアップができない
物理的にかさばる
これに関しては字のままになりますが、子供にとってはドリルやプリントなど勉強は毎日するものになるので日に日に増えていくことになります。
紙教材をとっている場合も定期的に配送されるものなので復習の為にとっておこうと思うとなかなかの量です。

復習のことも考えるとスペースに余裕がない場合踏み切りづらい要因ですよね。
書き込むと見にくくなる
紙学習の利点として直接書き込み、間違いやすい所や注意ポイントなど書き込むことができるところがあると思います。
しかし小学生の場合学年末テストなど、復習が必要となるテストもあります。
そういった場合直接教科書や問題集に書き込んだ間違えたところ周辺だったり注意ポイントが確認しづらくなるので要注意です。
書く事が面倒になる、飽きる
子供がタブレットを好む理由の多くが操作性やゲーム性、簡単に言うと手軽さになります。
反対に紙学習が嫌になる理由は自身で問題を読み上げ回答する必要があったり、書き込む手間が増えるところ。

やはり書くという作業に慣れていなかったり、そもそも勉強が苦手なタイプの子には苦手意識が強くなり敬遠しがちになってしなうようです。
復習のムラ
タブレット学習の場合間違えた問題に対して再度学習を催すアクションがあ ります。
しかし紙学習の場合保護者がきちんと管理しないと間違えた問題を再度学習し直す頻度はどうしても落ちてしまう、ということです。
保護者が管理せずとも管理してくれているタブレットタイプと、
保護者の後押しの元、苦手問題を克服させていく作業の差が表れるところではあると思います。
バックアップができない
タブレット学習の場合過去数年遡り学習できる(受講期間による、何年分かは教材による)システムが導入されているところが多くあります。
一方紙学習の場合バックアップ機能がないため教材受講の場合は過去にさかのぼることはテキスト保存以外方法がなく、
先ほど話した通りに場所をとるためになかなか難しくなると思います。
保存されていたとしても書き込みがあるために見づらく、確認しづらい状況であることが予想されます。
そんな中で復習や間違えた問題を選出することは容易ではなく、やはり保護者のサポートが必須になってきます。
紙学習のメリットでメリットを参考に
紙学習に向いているタイプ
- 勉強する習慣がすでについている子
- 出先で勉強することが多い子
- よく理解できずに間違えてしまってもくじけない子(負けず嫌い)
- 収納スペースに余裕がある
- 保護者が声掛けしたり、教える時間の余裕がある
のような家庭にに向いているのではないかなと思いました。
紙学習でオススメな教材はZ会!



ハイブリットという選択
ここまでどちらがどうでこちらがこう、というお話をしてきました。でも、

とさらに悩むことになった方もいると思います。
そんな時は【理解する為にタブレット、記憶するために紙】とうまく使い分けていくのも1つの手です。
どちらも片方では補いきれない利点がありますから、どうせなら両方の良い所取りしてしまおうってこと!!
教材によってはタブレットと紙どちらも導入し上手くサポートしているところもあります。
進研ゼミ、チャレンジタッチならタブレット導入無料で、紙学習の為のドリルもついてくる!
詳しく知りたい方はまず資料請求して、教材内容を見てみてください♬
紙教材をメインにして安いタブレット教材にも登録して理解、解説に使う。
逆にタブレット学習をメインにして、本屋さんでドリルを買ったりネットで無料プリントを印刷してやらせる。
ちなみに最安値タブレット教材はスタディサプリ!
実質月々980円で始められます♬
親に時間があまりない日はタブレットで勉強してもらい、余裕のある休日は一緒に考え教え丸付けをする。
子供目線で言えば親に時間がない時はインプット、余裕のある日にアウトプットをするということ。
このペースで続けられればうまい習慣の軸になると思います。

タブレットと紙、上手く使い分けていくことで子供の負担も親の負担も減っていくと思います。
組み合わせ例
- 進研ゼミのチャレンジタッチのみ(タブレットと紙教材がついてくる)
- スマイルゼミ+ネットの無料プリントor市販ドリル
- スタディサプリ+小学ポピーorがんばる舎
- Risu算数+ブンブンどりむ
などなどいろいろな教材と組み合わせて無理のない範囲(多すぎない程度)で継続していくことがポイント!
これは何に対しても言えますが続けられないとやっぱり意味がないなって思います。
継続して習慣にすることが大切です。
やりやすく合うものを正しく選んで親子で楽しめる学べることが継続の近道ですよ♬