子供が小学校に上がった学期末…
保護者として初めてもらうのが成績表ですね。
その後子供が学校に通う間もらい続ける成績表ですが、我が子の成績表を見ていると上がる疑問。
- 成績はどの様に付けられているのか
- どのように解釈すればいいのか
また、2020年度から新学習指導要領の導入で成績表の内容も変わっています。
この記事では実際に元小中学校で教論、学習指導や不登校指導・生徒指導などのカウンセリングをしていた
寄り添いカウンセラーQooちーさんにインタビューさせていただいて、
学校の先生の成績表の付け方・成績を上げるには?について伺いました。
学校の成績の付け方ってどうなってるの?

学校の成績の付け方はどう評価する?
Q:学校の成績の付け方は絶対評価?相対評価?それとも個人内評価?

個人内評価を加味した絶対評価で行っています。
解説!
絶対評価とは→成績のランクによって振り分ける
相対評価とは→あらかじめ人数が決まっている
個人内評価とは→個々の状況に応じた目標に対し評価される
個人の成績をクラスの他の生徒、学生の出来や教師によって課された学習の到達目標など、生徒の外にあるいかなる尺度によっても図らない、純粋の本人の内でのみ成績を考えるという評価の手法。
その生徒の前日、先週、先月の出来に対して、どう変わったかだけを評価するもので、その性格から「進歩の評価」ともいう。
以上を確認するとつまり個人内評価を加味した絶対評価とは、
個々の学習理解度や向き合い方などを前期の成績と比較しどれだけのランクに到達したかで振り分けていくことになりますね。
成績をつける基準
Q:成績をつけるのに基準ってある?

あります。
基本的に【観点別学習状況の評価規準】があります。そこにはABCの3段階での評価規準があり、3つの観点の合計とその他の評価を含めて総合的に判断しています。
基準の内容まで細かくはわかりませんでしたが文科省で学習評価に関することはいくつか記載がありました。
2018年のものですが、文部科学省が出す学習評価の考え方についてわかりやすい資料があったので記載しておきます。
※学校や先生に向けた資料
先生や地域での違い
Q:地域や先生によって変わることもある?

基本的に【観点別学習状況の評価規準】があるので大きく変わることはありません。
少し意地悪な質問ですが
「基準に沿ってつけるが、多少の前後はありうるということですか?」
とお聞きしたところ、
「そう理解していただいていいと思います」との回答をいただきました。
成績の評価に対する規準があっても先生の解釈などによって多少変わることもあるかもしれませんね。
気をつけていること
Q:成績をつける時に気を付けているところは?

子供達が今後意欲を持って取り組めるような評価にすることが大切だと思っています。
例えばですが個人内評価を加味した絶対評価で評価していますので、例えばBとCのボーダーにいる2人がいるとした場合、個人内評価の高い児童をBにしてあげ、頑張りを認めてあげます。
個人内評価が下がっている児童においては下げることにより今後の頑張りを促します。
同じラインにいた子供がいたら個人の頑張り・伸びに対し評価してあげることもあるそうです。
そう聞くと個人をしっかり見て評価してもらえているようで保護者としても嬉しいですね。
下がっている場合は苦手分野やテストの凡ミス、または提出物・授業態度などだらけてしまったりと様々でしょう。
なぜ下がったのか見極めて次学期に活かしていきたいですね。
成績をつける時期
Q:成績はいつ頃つけている?

管理職の点検を受けるので、終業式の1週間前頃には完成していないといけません。
管理職の点検では成績の付け方に関しては特に言われることはありませんが、文章表現の項目(道徳・総合的な学習の時間の記録、特別活動の記録、行動の記録などが文章表現になります。)に関してはかなり厳しく指導があり、書き直しも普通にあります。
またこの部分もある程度他の先生方と申し合わせています。その他に道徳・総合的な学習の時間の記録、特別活動の記録、行動の記録などがあります。
そして、その補充として、児童個人のがんばっているところや特に連絡したいことをお知らせしています。
成績に関して担任以外にも点検を受けるそう。
終業式の1週間前までには完成していないといけないということは、学期末テストが終了次第徐々に成績を出し始めていることになるのではないでしょうか。
成績の付け方に関して管理職から言われることはない様ですが、成績表にある先生からのメッセージには厳しい指導がある様です。
あの先生からのメッセージにはいつも心が温まります。
たくさんいる生徒1人1人に書くのはとても大変な作業!ありがたいですね。
成績をあげるためにはどうすればいい?
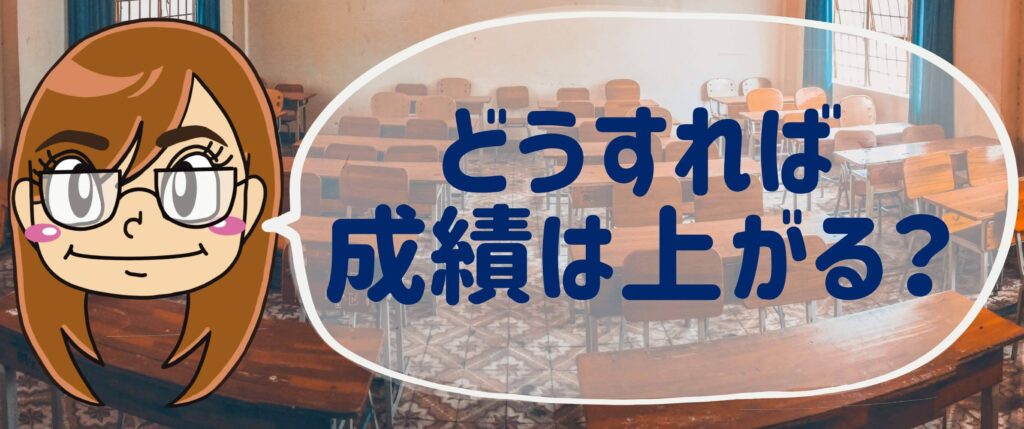
成績を決めるところ
Q:授業で成績に反映されるのはどんな所?

テスト、授業態度、ノート、発表、小集団での活動など様々な学習の様子。
提出物と成績
Q:提出物は成績にも関係する?

関係します。
その他成績を決めるとこと
Q:授業、提出物以外で成績に関係することはある?

授業、提出物が中心になります。
テストと成績の関係性
Q:テストには小テストや単元ごとのもの、学期末テストなどがありますが、平均を出して成績を出す? 学期末はその学期のまとめになることから重要度が高かったりする?

学年教師での申し合わせによって割合を決めています。
普段何気なく受けている授業やプリント・ドリルの提出、宿題なども成績に多少なり影響があることがわかります。
テストは完璧にできていてもそれだけではダメということですね。
成績を上げるには
Q:成績を上げるために必要なことはなんでしょうか?

テストの成績だけでなく授業に取り組む姿勢(発表、グループ活動、ミニ先生、黒板を使っての説明や補助など)
例えばシャイな子の場合で発表など前に出ることが不得意なら
→主に【思考・判断・表現力】の観点の表現力の部分になると思います。
表現力ではBレベルでは表現することができるか?が問われますが、
Aレベルになると、その単元の特性に触れながらの表現力が必要になってきます。
そこで、表現できない児童(Cレベル)においては友達と一緒に表現させたり、教師がアドバイスをこまめに出してあげるなどの支援を行い、Bレベルに導きます。
また、Bレベルの児童においては思考の部分を支援していきます。
積極的に授業に参加すること、参加しようと努力する姿勢も重要な様です。
ここからはさらに細かい評価の部分を上げるために必要なことを伺いました。
知識・技能を上げるには
Q:知識、技能の部分で高評価を得るには?

教科の特性に応じて、単元の性質を深く理解し、手際よく対応できる実践的な力をつけること。
教科の特性とは?
一例で解説します。
国語:新しく知る言葉や漢字はどのような意味があり、使うのか言葉の働きを捉え表現する。
算数:掛け算が出来ないと割り算ができない積み上げて学んでいく学習。
など、本当にさまざまでしょう。
国語は表現が多く、答えも一つとは限らない事が多いですが、算数は必ず一つの答えに導かれます。
教科によって特性があり、単元ごとの重要ポイントを見極めて学習していくと良さそうです。
実践的な力を求められているので、繰り返し復習したり少し難しい問題にも対応できる力をつけてあげたいものですね。
思考・判断・表現を上げるには
Q:思考、判断、表現で高評価を得るには?

ひとつの視点だけでなく様々な見方を持ち、その特性に触れながら考えたり説明できる力をつけること。
主体的に学習に取り組む態度を上げるには
Q:主体的に学習に取り組む態度で高評価を得るには?

時間ごとのめあてを持って取り組み、それを達成していける。そして、振り返りがしっかりとできること。また、単元に感心をもち、進んで学習ができる力をつけること。
この部分に関しては文部科学省のHPでも各観点の具体的な内容について、記載がありました。
コロナ禍集積が少ない場合の成績の付け方についてという内容の一部分ですが抜粋しておきます。
・ 「思考・判断・表現」の観点については、ペーパーテスト、論述やレポート、発表・グループでの話し合い、作品の制作や表現などの方法を
・ 「主体的に学習に取り組む態度」の観点については、ノートやレポート等における記述、授業中の発言、教師による行動観察などの方法を それぞれ例示しているところです。
成績にまつわる番外編

ここからは都市伝説のように聞いたことあるけど実際は!?と思う質問をしてみました。
生徒によってひいき
生徒によってひいき目に成績をつけることはある?

ありません。
良く聞く気に入った生徒をひいきする先生、なんてのはありません!
しっかり中立に見守ってくれているようです。
成績へクレーム
生徒の親から成績のクレームを受けたことはある?

ありません。
保護者間では先生の成績の付け方について不満を聞くことがたま〜にありますが、実際に直接先生へクレームを入れる保護者はいないようです。
なかなか勇気が必要ですもんね(笑)
中学受験する生徒
中学受験する生徒の成績は高めにつけたりする?

ありません。
ここでもしっかり中立を守り文科省の出す基準に沿って成績をつけているようです。
我が子が受験するなら気持ちでいいから内申点を上げてほしい!!と思ってしまいそうですが、実力をしっかりつけるしかないようですね。
今回は成績の付け方について調べていた際に出てきた
- 成績の付け方に贔屓がある
- クレームを入れると成績が上がる
- 受験する場合は先生に伝えると気持ち上がる
この3つを失礼ながら質問してみましたが、一貫としてその様な事はないと回答をいただきました。
上記の話が本当にあるのかはわかりませんが、個人をしっかり評価するための成績表なので当たり前といえば当たり前ですね。
子供たちとの接し方
最後に数十人の子供たちを日々よく観察したり、良いところを探したり全員と向き合うのはかなり大変な作業なことだと思います。
成績とは関係なく子供たちとの接し方に気をつけていることはありますか?

できるだけ児童の活動の様子を記録できるようにメモを取るようにしています。例えば、授業での発表や黒板を使っての説明などでもきっちりと回数や内容をその都度記録しています。
生活科などにおいては動画での記録をしておき、授業後にこどもたちの活動を見直すなどの活動も行わなければいけません。
普段からよく観察してメモまで取ってくれているんですね。
些細なことでもみてもらえているだけで子供のみならず保護者も安心を感じることができます。
今回は軸に「成績の付け方」がありましたが、この1面だけみても相当な労力が必要なことがわかりました。
さらには授業を工夫したり、時にはケンカの仲裁などやることが多岐にわたる先生には頭が上がりませんね!
どう見る?成績表の活用法
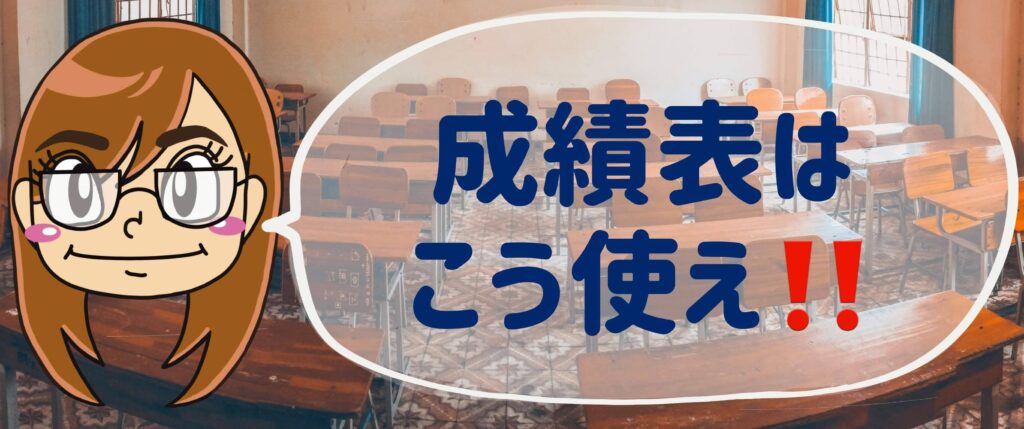
成績表が配られた時、誰もが確認するのはもちろん成績です。
でも成績表の数字を見て終わりなんてもったいない!
子供たちが数ヶ月学校で活動してきた成長の記録ですから、じっくり読み解いていけるといいですね。
成績の見方
もちろん1番に確認しなければならないのが成績の部分。
各教科に与えられた観点は3つです。
- 知識・技能技能(何を理解しているか、できるか、できるようになったか)
- 思考力・判断力・表現力(理解したことやできることをどう使うか、表すか)
- 主体的に学習に取り組む態度(粘り強く取り組んでいるか、予習や復習を行い学習の進め方など調整しているか)
今の成績はこの3つから評価しています。
さて文部科学省ではこの新学習要領について
「子供たちの生きる力を育み、明日へ、そして成長した先でも生きる学習を」とし、
何を、どのように学び、そしてできるようになったかの過程を大切にする教育を掲げています。
また今は学習でも自ら切り開く力が大事とされ、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、判断して行動する個性を生かす教育にも力が入っています。
何気なく科目ごとの総評に目が行きがちですが、ご家庭でもぜひ成績の過程を思い出してあげるといいですね。
宿題、テストの他にも家庭での予習・復習や家庭学習教材を利用する様子。
授業態度は見えなくても先生との面談で気になることを聞いてみるなどして、子供の成績に至る過程を振り返りながら確認するともっと見えることがあるでしょう。
伸びた科目があれば「あぁ、予習を頑張っていたよね」
下がった科目があれば「苦手な単元があったよね、長期休みで復習しようね」
など、過程を振り返るだけでたくさんの声をかける事ができます。
逆に過程を振り返らず並んだ成績のみを見てしまうと上がった下がったの情報しか目に入らないので、つい叱ってしまう原因にも。
子供は怒られるとやる気がなくなってしまうもの。
励ましたり、助言をしてモチベーションを上げてあげることも親の役目かもしれませんね。
所見の見方
俗に言う先生からのメッセージの部分です。
学校生活を過ごす中で頑張ったこと、成長したところなど、数字で評価できない部分に対し褒めてくれています。
また普段は見えない学校生活の様子が書かれているので、学校でどんな成長をしたか知る機会にもなります。

家ではなかなか見せない子供の一面などを知ることもできます。
できるようになった事は大いに誉めて、成長を喜んで応援していけるといいですね。
成績表は我が子の成長記録
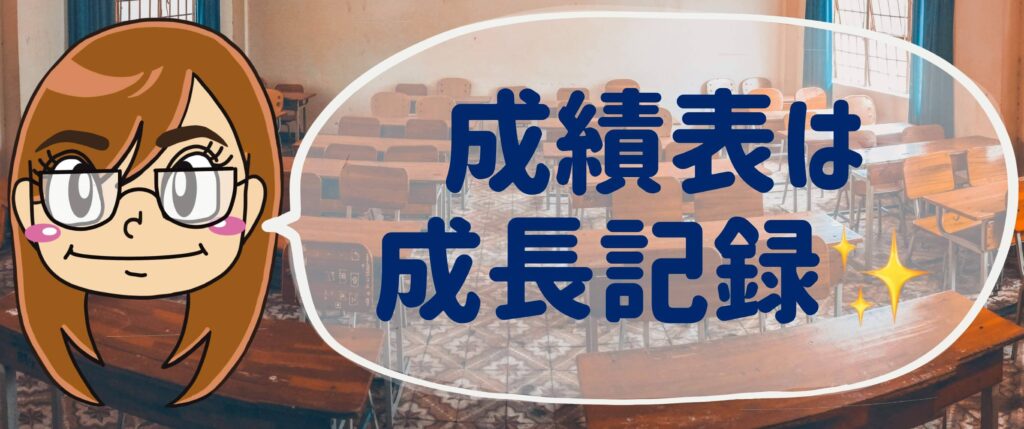
成績表はただ成績の上下を見るためのものではなく、何が頑張れたのか?どんなふうに成長したかが確認できる成長記録です。
成績をつけるために先生は常日頃から子供たちを良く観察してくれています。

成長は叱るためのものにしてしまわないように、その学期や学年を振り返りこれからどうするかを考えるための材料として考えましょう。
もちろん成績を伸ばせるならそれにこしたことはないですから、どの観点がなぜ良くなかったか親子で読み解いていけるといいですね。
その上で必要と感じたら教材や塾に通うことを考えていけばいいと思います。
でもあくまで子供が「たのしくまなぶ」ことが1番大切!
その方が頭にも入りやすいのも事実です。無理に強要することがないよう注意してくださいね。
